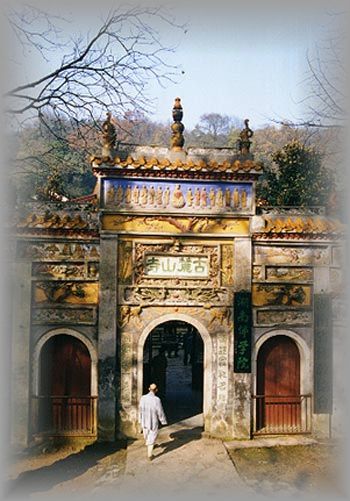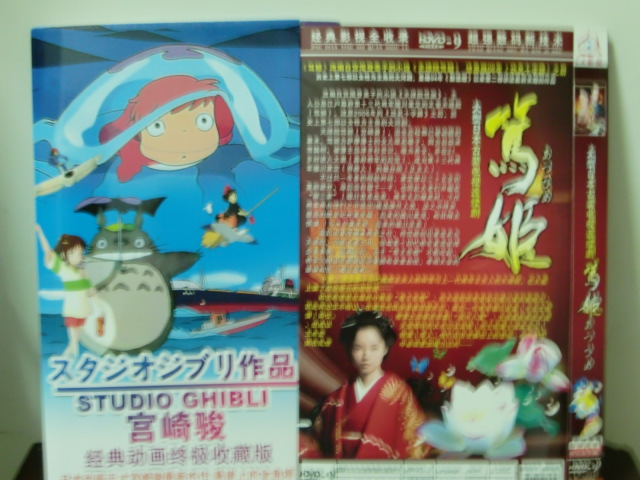全編まとめてこのURLへ新しく転載しました。◆
●福島顕二郎の長沙教師録〜未来への道が完成(文字クリック)
長沙長科日語学院の公式ホームページ
・
|

| 2009/03/10 竹田の子守唄は中国で |
朝はジェット機の発進音のような大音響が7時過ぎの朝空に響きわたる。 隣の長沙大学男子寮が発する目覚まし時計替わりのビートの効いた音楽だ。 彼らはこれでもか!という音響に抵抗しながらしぶしぶベットから起き上がるに違いない。 私はもう朝食をすませて朝の静けさを楽しんでいたのに・・・ でも今日はなんだか聞き覚えのあるメロディーが聞こえる。テンポもややスロー調だ。 あっ!私の好きな竹田の子守唄だ。 http://www.youtube.com/watch?v=vwjonOlpdmo この歌は中国の人たちにも愛されていたのか。 そう知ると、この名曲よ長沙中の大空に大声で響き渡れと思ってしまう。 授業の始めにこの音楽について生徒に聞いてみた。 ほとんどの生徒はこれは中国の歌だと思っているらしい。先生これは悲しい子守唄ではなく、「希望の祈り」の歌ですよと言う。 よく聞いてみると文化大革命が終結した1980年代に新生中国に託して作曲された「祈祷」という歌だそうだ。 苦しい時代からやっと明るい日差しが見えはじめた頃、大衆の希望の祈りがこの「祈りの歌」を中国中に根づかせたそうだ。 もとより生徒達の生まれる前の歌だが、みんなこの歌が好きなようだ。竹田の子守唄の悲しくつらい歌詞もみんなに話した。 そしてこの歌を日中2つの歌詞で合唱し過ぎ去った昔を互いに思い浮かべたのだった。 (中国版)「祈祷」 生徒の抄訳から ここに希望の鐘を鳴らす祈りがある。 失敗は失せ 永遠の成功がここにある。 地球は動きを忘れ、夏、秋、冬の季節もなくなる。 宇宙は天の窓を閉ざさず、太陽は西の空に沈まな い。 「祈祷」は下をクリックしてください。 http://www.youtube.com/watch?v=_8cLMPt4HtM&feature=related |



| 2009/03/6 隣の人は何する人ぞ |
宿舎は学校の敷地の隅にある。 壁を挟んで小さな家が立て込んでいる。朝早くから大きな声が聞こえる。掃除をしながら何やらぶつぶつ独り言をつぶやいているようだ。 「うるさい人だなあ」と閉口していたが毎日同じような話だ。 いやこれはひょっとすると「巷に隠れた導師様のお教えかもしれないぞ」そう思ってみるとそのようにも聞こえる。 目覚まし時計のような早朝の呪文の謎は深まる。 昨日の深夜は隣りから大声で派手な夫婦喧嘩がきこえた。女房殿の金切り声が夜の四十万に響きわたる、8割は女房の声だ、会話は全くわからないが、推し量るに 「この飲んだくれの甲斐性なし、わたしゃ毎日あくせく働いているのに、あたしの着物ひとつ買えないじゃないか、どうしてくれるんだい」 「なにおーこの馬鹿野郎おれも・・・」 亭主はわずかに反論?隣近所はああまた始まったか!と子守唄代りに聞いているのだろう。 「うるさい!」なんて野暮な怒鳴り声など聞こえてこない。山本周五郎の世界のようだ。早く中国語を覚えてこの謎を解かなければ! |

| 2009/03/5 生の日本語と話ができた |
金曜日の午後は自習時間になっており生徒も少し余裕がある。夕方から804教室(半年組)の生徒7人が宿舎に訪ねてきた。 スーパへ買い物に出かけ台所で夕食の準備をする。 生徒の宿舎は台所がなく料理ができないので、ここが腕のふるいどころと懇親の場と化す。 私にとっては一石二鳥で嬉しい。 夕食のあと日本の我が家にSKYPEで妻と交信する。みんなパソコンの前で緊張する。はたして自分の言葉が生の日本人?に伝わるでろうかと不安だった が、しかしなんとか話ができた。緊張が笑顔にかわり喉元で引っかかっていた言葉が次々と流れる。 言葉とはなんであろうか。友好の夜は更けていく。 |

| 2009/03/4 日語学校 青春群像1 |
704教室(1.5年組)の魏君が帰ってきた。 突然、お父さんを交通事故で失くした傷心癒えぬ身で痩身痛々しいが根っ子の太い偉丈夫だ。 見事日本語能力試験1級を合格し、みんなの憧れの的でもある。 そんな彼が開口一番「はるばる日本からいらっしゃった先生に挨拶が遅れてすみません、私にできることをさせてください」と言う。中国の人々の裾野は広い。懐の深さと誠実を彼にみた。 周さんと陳さんは704教室(半年組)の仲良し女性2人組み。周さんは班長、陳さんは大らかなスポーツ女性。昼と夜の食事は校門前の小さな食道で取ることに決めた。 そこで食費を切り詰めるため店の主人と交渉した。昼夜2食で1ヶ月300元(4500円)で契約成立。 もとより1人分ではなく2人分のの値段だ。交渉のしたたかさは伝統か。2人とも6時に起きて授業前の勉強をする。余裕は本代に当てているようだ。 |

| 2009/03/02 日本語能力試験の発表 |
朝から教務室のパソコンに生徒が群がっている。 今日は12月に行った日本語能力試験の発表だ。 中国ではインターネットで受験を申し込み、結果もネット上で個々に発表される。 みんな自分の受験番号をインプットして結果を見ている。合格が出るたびに大きな歓声があがる。 もとより日本語学校で一生懸命に勉強している目標は日本語能力試験の一級合格を取ることだ。 1年から1年半の勉強後1,2級に挑戦する。2級は沢山の合格者が出たが1級は難関である。 それでも8名ほどの合格者が出たようだ。2007年のデータでは1級の合格率は26%、受験者は中国全体で1級が約7万人、2級が11万人と発表されている。 日本に対する関心。期待の深さにあらためて驚く。海外受験者は国内受験者に比べ特に聴解(ヒアリング)がやや弱い。 この学校で自分の担当は会話である。活きた会話を少しでも多く行い彼らの助けになるような授業ができるよう頑張りたい。 |



| 2009/02/27 中国文化です |
夜半から雷が鳴る。 枕元の電球がつかない。停電だ!日本では久しく経験していない。雷さまの声もゴロゴロではないかもしれないぞ。 薄暗闇の中でパンとコーヒの朝食をとる。山登りのテントの中で食べた夜食を思い出した。 そうだ!ここは中国なのだと思い直す。授業の後で生徒の陳さん、頼さんと蒸料理の店に食事に行く。 こざっぱりしたおいしい店だ。簡素なテーブルを囲んで話に花が咲く。 勘定を払おうとすると2人がもう済ませていて取ってくれない。 先生に御馳走するのは中国の文化ですと言う。年長者が御馳走するのが日本の習慣だよと言っても笑って取り合わない。 「師敬う」の論語の世界に来たようだ。果物を買って渡すと恥ずかしげにお礼を言われる。これが中国の習慣ですとは言わないところが奥ゆかしい。 帰りに2元(30円)店を見つけた。りゃんユワン(2元)、りゃんユワンとスピーカーがけたたましく叫んでいる。 100円ショップファンの私はすぐに飛び込んで拡大鏡を買ってしまった。 習性は恐ろしい。中国の大河は時には氾濫もするが今なお3000年の歴史を漂わせ悠然と流れているようだ。 |
![]()